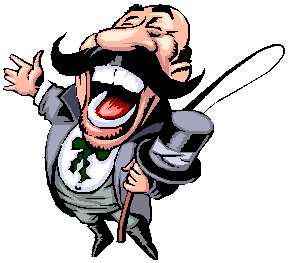|
#001.
MILVA
クラブといった感じの小さなステージ。テレビのセットかもしれない。
しかし、一曲ごとに舞台も声も移り変わっていく。
一曲目はリリー・マルレーン。ゆっくりとした動作…
a音でよく下あごが動くな、と感じる。目はほとんどつぶっている。
二曲目、まだ動きはゆっくり。しかしハスキーで、小声にしても
しっかり音が入っている。どんな風に扱ってるんだろう?
次の曲は短調でタンゴのリズム。いきなり前の2曲とイメージ変わる。
しぐさを入れて、語り、叫びを合間に。しかし曲から決してはずれない。
シルクハットをかぶり直して、指先で失敬…それまでに決まりまくってるから、
ちょっとくらいキザでもカッコいい。
今度はジャズ曲だ。歌詞も英語を歌っている。あんまり下には入れない声に
なっているのかな?低音でも軽くした感じになっている。
ピアノにちょこっと座ってピンク色の照明、この辺から既に創り上げているのだろう。
次はシャンソン。ちょっとおどけた感じ、振りつけも声も。
歌詞もしっかりフランス語で歌ってる。しかし、ダミ声ぽくウォーと張った後に
すぐ囁き声…面白いし、凄いなと。声楽の方ではちょっと無い表現では?
そして、オーソドックスにカンツォーネの大曲へ。
とにかく、この声量…。響きに持っていってる感じではないのに。
その次は「ジョニィ」。歌の途中で床に寝ている男に語りかける感じで。
そして、髪の毛パタッと倒して終わる。役者だな…と。
「待ちましょう」。バイオリンの人と背中合わせで楽しそうに。
el mio cuo、たったこれだけでも一瞬で深く入れて浮かせている。
何曲か続く…間奏の時の動きもサマになっている。顔の表情に合わせて
声も本当に良く変わる。語るような所でも、演説みたいに訴えかける所も
あるし、すぐ小さくもできる。演奏でブレイクした後に軽快なリズムに
なる所も、切り替わった感じをすぐに出していく。
「oi vita mia」と言っている曲で、叫ぶ所も何回かあった後、
最初のリリー・マルレーンに戻り、再びゆっくりとした動き。
何もかも計算されているのか。それがあったうえで、
数え切れないアドリブを繰り出しているのか。
2回目に観て感じたのは、とにかく「この人は役者だ」。
声の感じからリズムから、しぐさから全てを含めて表現に注ぎ込む。
自由にやる所はやるし、踏まえる所はきちんと踏まえる。
その幅が恐ろしく広くて、自分にはまだ到底分からない所もある。
【「ミルバライブ」】
#002.
JANIS JOPLIN
彼女のアルバムを聴く限り、あまり強く魅かれることはなかった。
決して上手いヴォーカルだとも思わない。大好きな曲もない。
でも、この映像を観て彼女という人間が好きになった。
「何も考えない、感じること。瞬間と一体になる、宇宙なのよ」
ということばも、彼女なら素直に納得できる。
モントレーのあのステージは、何度観ても鳥肌が立つ。
“歌”が“歌”でなくなる瞬間を観るのだ。
あの大会場を真空にしてしまうようなパワーだ。
「子供が泣き叫んで訴える」というのは、まさにこれなんだと気付く。
話すように歌い、歌うように話す。歌の中で怒り、泣き、笑う。
「私は未だパワーだけ」と語ってた彼女にいつかが来なかったのが本当に残念。
彼女がアレサやオーティスの表現力に関心を寄せていたのが興味深い。
歌には確かに技術が必要で、しかし、その技術をあやつり、
創るのは「強烈な想い」であり、その人が培ってきた「たましい」なんだな。
▲トップへ戻る 【「ジャニス ア
フィルム」】
#003. AMALIA RODRIGUES
何かが違うのではないかという気がしてしょうがない。
今まで「耳が聴ける」ということがわからないとは思っていたけれど、
心の底から全くわからないとは思っていなかった。
それが何なのかは全然わからないのだが、
今初めて「何か違う」ということばが私の頭に飛び込んできたのだ。
アマリア・ロドリゲスはピアフとは違うけど、
同じようにことばが後から後からかぶさっていくようなところがある。
そのリズムについていけない。追いついたと思ったら待ってるし、
こっちがひと呼吸おいてる間にもう走り出している。
それは曲がスローだとかアップテンポだとか、そういうことでの違いじゃない。
とにかくつかまえられないのだ。
曲が始まると、どんどん滑り出していくあの感覚は、私にはわからない。
ファドというジャンルは、
歌詞をみるとポルトガルという国の歴史や国に対する想い、
生活している人々の姿など、いろんなことがわかる。
決して明るい曲ではないが、強く生きてゆこうとする姿勢がみえる。
イワシの歌なんてかわいらしいのだけど、
アマリアが歌うと、歌詞のことばの世界が音によって、
どんどん広がっていくのがわかる。
アマリアのように、生きてきた中でのつらいこと、苦しいことを、
歌にすることができるというのは幸せなことだ。
ステージに立つアマリアは存在感に溢れていた。
黒の衣装で身をつつみ、ほとんど動きもせずに、あごを少し上にして歌っていた。
あごをすっと上にしたまま歌っていて苦しくないのかと思ったけれど、
あれが彼女のしぜんなスタイルなのだろう。
歌うということは自分の感情を一つの世界にして伝えるだけだ。
本物は皆そうだ。何も余計なものがついていない。
ことばを音に乗せ伝えるだけ。(K) ▲トップへ戻る 【アマリア・ロドリゲス ライブ】
#004.
JULIETTE GRECO
絞首刑にされようとする女の人の歌がすごい迫力で、
客席も入り込んでいるのがわかった。
それと「行かないで」のフレーズ。黒のシンプルなワンピース。
20分の休憩のあとも衣装がえなし。バックのセットもなし。
ずーっとスタンドマイク。ピアノにアコーディオンに超シンプル。
バンドの人の名前を紹介したとき、歌っているかのようで歌詞かと思ったら、
ドラムの人の名前を呼んだんだと判明。
ああ、憧れのパリだ!この言語の差は何だ??
70過ぎても声って出るよなあ。それもかさかさしてなくて潤ってる。…うらやましい。
歌詞の中に「人はすぐに忘れるんじゃなくて、すぐに慣れてしまうのさ」って。ドキッ。
シャンソンは結構思想的というか、哲学的というか。
最後はすごい底までずーんと入り込んでいるのがわかった。
客席の50代の人たちはたぶん、1970年前後によく聞いていた人たちだろう。
グレコは昔サルトルたち実存主義者の思想家、詩人、文化人の溜り場であった
パリの地下酒場「タブー」のマスコット的存在だったらしい。
70過ぎた今も、所作や雰囲気に可愛らしさは残っている。
ひとくちに洋楽だの、ジャズだの、シャンソンだの、
西洋人だの言うけれど、アメリカとは全然違うやん。
シャンソンってなんか哲学やん。
すごい、わび、さび利いてるやん。(M)
▲トップへ戻る
【ジュリエット・グレコ ライブ】
#005.
PAU CASALS
感動した。うなづくことが多かった。
おじいさんになったカザルスが、劇場で演奏する前に言った言葉には、
もう何も言わず拍手を送りたい。彼をいとおしく思った瞬間だった。
かつての国家カタロニアの小さな村サン・サルバドル出身の彼は、
地方出身者らしい知恵、粘り強さ、目的意識、負けん気を奥に秘めた努力の人。
長い間の不幸な結婚の後、年老いてから出会った二人には幸福をもらった。
故カプデビラ夫人と、マルタ未亡人だ。
それまでの彼の音楽が人々に幸せをもたらせたとしたら、
当然与えられるべき至福のとき、安らぎの時間だったろう。
彼の人となりを語る人々の言葉は皆正直で、時折辛辣な批評もある。
しかし、gentleで愛情を含み、思い出しながら幸せそうに
感慨深げに語っていた。ひとかどの大人とはああいうものなのだろう。
その中のひとりがカザルスの音楽についてこう言った。
「彼の音楽はただ完璧に演奏するだけではない。
彼は常に聴衆に何かを訴えてきた。しかし、その音楽は
詩のように純粋で簡潔なスピーチのようだった」と。
彼には才能があった。しかし、それ以上に努力家であった。
幼い頃、始めて弦楽四重奏を聴き、父親にチェロを習いたいと告げた。
父の手作りのヒョウタン・チェロを与えられ、彼がアベマリアを弾くと、
一同は感動した。とりわけ音楽家の父より母の方が彼の才能を見出し、
あちこちに連れてはチャンスを作ってくれた。
バッハのチェロ組曲は難曲だという。
並みの練習量では演奏できる程になれない。
彼はこの曲を長年研究し、発表し、そして成功した。
彼は宝石細工師のようだったという人もいる。
音楽は完全に大きな視点でとらえ、しかし、細かいところも忘れない。
彼自身は言う。自然が好き。
自然にしていれば音楽が要求するものを組み立ててくれると。
祖国の独裁者フランコ総統に反対し、亡命したカザルス。
もうほとんど人生の終りに近い老齢で、若く美しい乙女マルタと出会う。
彼女はチェリストとしての才能もあったし、女優でも他の仕事でも
きっと成功していたであろう程の才能の持ち主だったが、
巨匠と出会ったことで、彼が生涯を閉じるまでの17年間を、
全ての時間を彼に捧げた。
彼女はカザルスの母親と同じプエルトリコ人で顔立ちや髪の色、
雰囲気など、風貌が母親にそっくりであった。おまけに不思議なことに、
マルタの母とカザルスの母は誕生日が同じだったという。
彼の才能を見出した母―当然彼は母を一番尊敬しているし、愛している。
その母と結婚した、と言っても過言ではなかった。
劇場での彼の言葉が忘れられない。
“ Cataluna was a great nation in the world.
I play a short piece of the Catalonian folklore ― Song of the birds ”
「鳥の歌」は、彼が最も愛し、今はスペインの一地方になってしまった
祖国への想いが込められた曲であった。
▲トップへ戻る 【パブロ・カルザス 鳥の歌】
#006.
CHARLES AZNAVOUR
彼の歌は、とにかく自然体。
「ほら歌っていますよ、ハイ、歌ってるんですよ、どーだ!」
などという、外形のラインが全く感じられない。
アズナブールは、強い表現をしているときも、
ツンツンと尖ってなくて、柔らかい感じがする。
音色だけであんな感じになるのかな?
どうしてゴチゴチにならないのかなあ?
音量をある程度出して、フレーズを大きく作った上で、
優しさ、丸さ、穏やかさを出すというのは、本当に難しい。
自分で無理にかけている圧力を解放してあげなければ、
アズナブールのような自由な表現はとてもできそうもない。
フレーズの作り方にしても、音色にしても、
体のコントロールと気持ちの余裕が先ず必要。
彼があまりにも演技派なので、
ついついそれに乗せられているんじゃないか?と思い、
目を閉じて聴いてみた。・・・語っている。
なんてさりげなく、ポンと吐くように、音を置くのだろう。
けれど、胸にチクッとくるような切なさが残る。
目を閉じていても、観せられる歌だ。
彼は、根っからのロマンチストなんだな。
あと20年くらいしたら、ツボに入ってしまうかも。
いや、こう思ってしまったということは、
すでにアズナブールの魔術に引っかかってしまったということか・・・。(Y)
▲トップへ戻る
【シャルル・アズナブール コンサート】
#007. MILES DAVIS
マイルスの眼光は、いつも何かを睨んでいるようだった。
演奏しているときも、他のミュージシャンに指示を与えるときも、
まるでケンカを売っているかのような威圧感がある。
その鋭い視線の先には、僕たちが想像もつかない音の世界が
広がっていたに違いない。彼は、いつでもそこに勝負を挑んでいった。
マイルスの音が炸裂するとき、
僕たちはその強烈な音の一つ一つにしびれまくるんだ。
もっと聴かせてくれよ、マイルス。もっと吹いてくれよ、マイルス。
僕たちはどんどん欲求を抑えられなくなる。もっと、もっとだ。
でもさ、あんな涼しい顔して、正直困ってたと思うぜ。
いや、ジャズ界の帝王・マイルス・デイビスが困るわけ、ないか。
時代とともに、マイルス・デイビスの音楽スタイルは大きく移り変わっていく。
だけど、それぞれに全く違うマイルス・デイビスがいた。
ずっとうつむいたまま、トランペットを吹き続けるマイルス・デイビス。
ぽつり、ぽつりと、音が鳴り出したとき、僕たちは静かにその音の跡を追うんだ。
でも、誰にもマイルスがそこからどうするのかなんて、わかるわけないよ。
そりゃそうさ、いつだって僕たちは彼の身体から溢れ出すエネルギーと、
彼が描き出す音のイマジネーションをみたいんだから。
でも、いつだって彼は答えてくれるんだろ?
僕たちがそれを求め続ける限りは・・・
僕はアクセルをガンガンにぶっ飛ばして、
あたりかまわず荒れ狂うようなマイルスの音が好きだ。
「オレのいっていることがわかるか?」
一番最初に聴いたマイルス・デイビスの音は、誰かを挑発しているようだった。
だけど、今日ある曲の途中で、急に涙が出てきた。
なぜだかわからないけど、涙が出てきてしまった。
マイルス・デイビスの演奏で泣いたのは、これが初めてだ。
「タイム・アフター・タイム」
確かに僕がこの曲を好きだからかもしれない。
いや、違う。
マイルス・デイビスの音があまりにもやさしかったからだ。(H)
▲トップへ戻る 【マイルス・デイビス ライヴ】
#008. CESARIA EVORA
西アフリカ島のカボ・ヴェルデ共和国という小さな国の
「モルナ」という音楽ジャンル(?)の歌い手。
60歳位で、フランスで火がつき、世界の市場にデビューしてから
まだ10年余りだそうだ。
ブエンナ・ビスタのキューバ「ソン」のイブライムやコンパイもそうだが、
植民地の頃は、夜の街も賑やかで仕事も多かったが、
共和国になったり、革命後とか独立後、生活に苦労するケースはよくあるらしい。
セザリアは裸足ですっくと立っていた。
彼女の国の歌は、とても哀愁の感を起こさせる。
彼女の何がすごいかっていうと、とにかく、何もしていない!
歌らしいことは何もしてない。
左手にハンドマイクを握ったら、握ったまま、反対の手をあげることもしなければ、
悲しそうな、嬉しそうな、日本にはびこっているような、
借り物の、形骸の、演劇じみた表情は一切しない。
「ようこそおいで下さいました。サンキューベリーマッチ」風の愛想も一切なし。
曲の最初から最後まで全部自然な地声。
ファルセットだの声楽のなんとかいう技巧も、或いは逃げも一切なし。
彼女にとって高そうなキィも、低そうな音も一切なし。
すべて同じ状態で引き受け、音声ですべての情感を表現していた。
予備知識全然なかったに関わらず、不思議な感動が沸き上がった。
繰り返しの時、音楽のリフレインって、何て気持ちいいんだろうと思った。
声ひとつ引っさげて諸国漫遊できる人だ。両手を合わせて(心の中で)拝んできた。
途中、小休止のバンド演奏の時、テーブルに腰掛けて、タバコを一服し始めた。
アメリカや日本のショービジネスだと、そうすること自体演出であったりするが、
ホントそれが習慣、生理的な欲求なのだ。あまりに自然体なんで笑えた。面白い。
ボサノバみたいに表面さらっとしてて、水面下に支えるテンションを要する音楽。
間奏で外人のカップルが踊っていたのを、タバコをくゆらしながら満足げに眺めてた。
アレくらい何もせず表現できたらいい。
こんど生まれてくる時は、南の国で、10人くらい子供を産んで、大きいお尻をして、
家族そろった時には、五枚重ねのパンケーキを嬉しそうに食べて、
いつも歌を口ずさんで、ゆれててっていうのもいいなあ。
去っていく後ろ姿は、何者も恐れていない迫力満点のおかーちゃんだった。(M)
▲トップへ戻る
【セザリア・エヴォラ ライブ】
#009. RAY CHARLES
1930年にアメリカ南部の黒人に生まれるというのは、何を意味するか?
差別と貧困のなか、6歳の時緑内障を患い、7歳にして完全に視力を失う。
5歳の時弟が溺死、14歳にして母を失い、15歳で父とも死別。
自立を否応なしに迫られ、シアトルに渡り、音楽のキャリアをスタートさせる。
幼少の頃隣家はジュークボックスを置いているような店を営んでおり、
ショーマンシップ溢れるジャズやブルースシンガーに心酔する。
また足しげく教会に通い、ゴスペルに親しむ。
ゴスペルを礎に、R&Bやカントリーに自身の色づけ“聖と俗”を融合、
彼の生み出した音楽は“ソウル“と名づけられる。独特のスローテンポ。
貧しさと孤独にあえいだ青年は、20代の終わりには、
アメリカのトップスターに登りつめ、高級自家用車に自家用飛行機も有していた。
精力的に仕事をこなし、数々の女性と浮名を流し、
薬物中毒に10数年苦しむことになる。いま生きていることが奇跡だという。
当時はそれこそ命が首の皮一枚でつながっていたと。
40年のキャリアを過ぎてなお、1年のうち10ヶ月をツアーで過ごす。
今までずっと好きなことがやれて幸せ、感謝している。
コメントを述べているミュージシャンがいうには、
アメリカ人はみなレイのように歌いたいという。
彼の声には、古い金管が通っていて、あらゆる感情を表現できる音色があると。
ニュアンスや音色を聞き分けられる耳を持つ民族。
“音楽“として評価することのできる人たち。
日本だったら、レイのような盲目のミュージシャンが、
若者を熱狂させる(ど真ん中の)スターとはならなかったに違いない。
また歌唱表現の裏に隠された生い立ちや、
苦難や迫害の歴史の上っ面をなぞっても、
何も分かりはしないかもしれないということを、心しないといけない。
恋の歌も、真意は実のところ人種差別を歌っていたりする・・・。
イメージ豊かで独特の音楽的解釈を施すことのできる天才。
体を揺らしながら、個性的な歌唱スタイル。興味深かった。
幼少から音楽と密接に過ごた体験の豊かさ、
否が応でも自立を迫られて始まったキャリア、辛苦を舐めた人生。
孤独も自立も絶望もないところで、ぬくぬくと同じ表現ができるのか。
作品のバックボーンへの配慮や、敬意が必要だ。
“スタイル“というのは、個人のソウルを通して体現したとき、
たまたまそういう形になったもので、
形だけ真似れるものじゃないのだろう。(551)
▲トップへ戻る
【レイ・チャールズ「ザ・ジニアス・オブ・ソウル」】
#010.
GILBERT BECAUD
私はこの人で、シャンソンに対する自分のイメージを根本から覆された。
フランスでは60年代後半、世界的な潮流だったロックが
他国ほど流行らなかった。
その原因はこの人にあったのでは、と言われているらしい。
ステージングからして、一般的に日本人がシャンソン歌手に抱くイメージとは
全然違う。確かにいつも紺のネクタイにスーツという出で立ちではあるが、
ピアノの鍵盤を叩きつけ、舞台を所狭しと駆け回り、
時に叫び倒したり、じっと観客を見つめて黙らせたり。
シャンソンもカンツォーネと同じく仏語で「歌」という意味で、
特定のリズムとかコード進行を指すものではない。
現にベコーの歌っている曲のジャンルは相当多岐にわたっている。
確かに王道、いわゆる、というのもあるが、このビデオを観ただけでも、
ジャズからロシア民謡やゴスペル風、フォーク調など様々だ。
ベコーという一つのジャンルの音楽ともいえる。
どういう音楽をやってもブレないのは、その人の個性が揺るぎないからだろう。
ビデオは「旅芸人のバラード」からだったが、
ともかく手の動きとかも含めてしぜんであり、なおかつ強烈な印象を残す。
曲にもよるが、ベコーの攻撃的な歌い方、ステ―ジングは、
当時のシャンソン界では賛否両論真っ二つだったそうだ。
「扇動家だ」「歌手生命縮むぞ」と言われても、彼は自分を貫いた。
そのことを、結構私はカッコいいと思ってしまう。
そういう歌い方にもかかわらず声楽出身だったり、
オペラの舞台をつくったりもしている。その辺がよく分からなくて意外だ。
「プロヴァンスの市場」という曲では導入部からマーチのリズムが入ってきて、
一旦ブレイクしてまた流れが変わる。その度に歌でも「変わって」いる。
特にマーチの所ではまさにたたみ掛け、街道でこれはどうですか、
こっちも安いよ、と八百屋さんが言っている感じだ。
声楽ではまずあり得ないだろう。
「せり売り」という曲ではそれがもっと極端になる。
ベコー自身「3通りの歌い方を1曲の中でしている」と言っているが、
バイオリンが早口言葉のように絡むのに合わせて、
ベコーの競売の早口語りが繰り出される。でもリズミカルだし、メロディもある。
リズミカルというのを、ベコーは「言い切り」で生み出していると感じる。
「チャーリー天国は無理さ」という曲は、パーカッションもコーラスも入る
楽しい曲だが、これはベコーの音程が高かろうが何だろうが、
言い切りまくる歌でないともたない。
やはりこの盛り上げ方は、素直にカッコ良いと思う。
「詩人が死んだ時」の曲では、ベコーはほとんど歌ってなくて、
お客さんに歌わせている。でも、凄く感動的だ。それが何故なのか。
お客さんとの場の形成も含めて舞台ということなのか。
私自身、発声でずっと悩んだりしているが、声が出たからといって、
それで舞台が成り立つ訳ではない。発声の仕方を変えたからといって、
それで持つほど歌の世界が甘いものであるはずがない。
一朝一夕で得られるものでないこと百も承知で、必死でなければ。
ベコーのように自分のスタイルを持ち潔くありたい。(407)
▲トップへ戻る
【ジルベール・べコー「そして今は」】
#011.
JAMES BROWN
ブラックゴスペルのパッショネイトの裏にある、辛苦と差別の歴史を、
島国のわたし達がとうてい理解できるはずはない。
力強い声も、超人的な筋肉やリズム感も、
その引き換えに神様が与えたのかもしれない。
ホントに深い悲しみや苦しみというものは、「聖者の行進」のように、
お葬式の内容でさえ、軽妙さとリズミカルさを生みだす。
教会を生活の一部とし、賛美歌で神様を思うことによって、
トランスレーション、麻薬のようにハイになれる彼らの歌を、
旅行みやげのまんじゅうみたいに扱っていいものか??
イエスさまを身近に感じることはできなくても、
何かしらの神を自分の中に感じて、感謝や生きる喜び、
尊敬を持って捧げることは多少なりとも可能かもしれない。
また海の向こうの文化を何かしら感じることが出来るかもしれない。
4つの時に両親が離婚、売春宿で大きくなる。小麦粉の袋を衣服にして、
不適切だと学校から帰されることもしばしばだった。
15歳、盗みのかどで3年の服役。父と掘建て小屋にいた幼少の頃、
林の中でひとりぼっちの時を過ごし、誰も何もしてくれない。
何事も自分で切り開くものだというのをからだで知っていたという。
JBのショーの観客はずっと昔から総立ちで踊りまくっていた。
ヨーロッパツアーで初めてディスコという箱を見た時も、
さして気にとめてなかったし、根付かないと思ったという。
彼はディスコミュージックは、あらゆる音楽のつまみ食いだと語った。
黒人の子どもがドロップアウトせず、学校を続けられるようなキャンペーンを、
副大統領に働きかけ、自らラジオ局を買い取って行なった。
政治的発言で世間から虐げられた時代も経験。
命狙われるかもしれないのに、いまこれを歌うって使命感があったのか?
挑まれると強くなれるのか?
本名の自分と、「James Brown」という2人の自分がいて、
その虚構のイメージに追いつくべくやってきた。
「James Brown」というもう1人の自分は、全くもって観客のものなのだという。
自分は決して“ジェームス・ブラウンさま”ではないと。
鏡の向こうのように俯瞰(ふかん)している。
ひとかどの人物やスターというものは、世の中に対して、
奉仕したいという願望を持っているものだ。
エンターティナーであり、政治的権力を握ることがなくても、
その思想や願いに確固たるものを持っている。
JBは運動神経バツグンだったらしく、
プロ野球選手やボクシングを目指していたようだ。
何より身軽で頭の回転が速かったんだろな。
あの魔法みたいな“WAO〜!”って野性的な雄叫び、丈夫なんやなぁ〜。
才能と引き換え、戦国武将のように、ヒトや世の中や多くの裏切りに会いながら、
満身創痍でまっすぐ進んできた。自分の王国も治めてきた。
そんな骨太のリーダーたちに社会はいつも支えられてきた。(pepo)
▲トップへ戻る 【「俺はJBだ!」ジェームスブラウン自叙伝】
#012.
MISORA HIBARI
小さなひばりさんの体から、悲しみは涙と共に、喜びは笑顔と共に、
歌となって溢れ出してきます。
でも、その溢れ出す量が、今まで見たミュージシャンの中で
一番多いと言えばいいのでしょうか。いい言葉が見つかりません・・・。
そして、驚きや感動と同時に起こる拒絶感。
それがどこから来るのかというと、
たぶん“エンターティナーとしてのあまりの巧さ”と、
“感情表現の振り幅のあまりの大きさ”にあるような気がします。
“エンターティナーとしてのあまりの巧さ”については、
巧すぎて嫌味ったらしく感じるということです。
大人が何を喜ぶかを熟知していて、大人にとても可愛がられる子供がいますが、
それを第三者として見たときに感じる嫌悪感、それに近いような気がします。
その感情は、生理的な嫌悪感に加え、嫉妬等、
様々なものが混じっているのかもしれません。
“感情表現の振り幅のあまりの大きさ”については、
これが同じ人間かと思えるほど、感情表現がくるくる変わっていく点です。
涙を流して歌った直後に、輝くような笑顔で歌うとか、そういうところです。
そのギャップがふと信用できなくなり、恐ろしくなるのです。
無邪気で可愛く見えて抱きしめたくなったり、
母性を感じて抱きしめられたくなったり、そうかと思えば、ゾッとするような厳しさ、
怜悧さを感じて戸惑ったりと、感情的に振り回されてしまいます。
しかし、そのようなギャップや深みは、ある程度以上自分を高めた人は、
必ず持っているものだとも思います。実際に会った会ってないは別にして、
スポーツ界の偉人、経営者、ヤクザの親分など、
何か厳しいことをくぐり抜けてきた人に共通する私の印象は、
優しさ、冷たさ、甘さ、厳しさ、などがそれぞれ強烈で、
しばらく接していると、その人の人間性が分からなくなることです。
そこで考えるのは、人はいろんな苦労や経験を重ねていくと、
それぞれの感情が深く強くなっていくのだろうかということです。
ひばりさんのステージを嫌味ったらしく感じるのは、
私に苦労が足りないために、その感情の深さについて行けないからであって、
私がもっと様々な経験をして成熟した時には、もっとストレートに感動するか、
完全に拒絶するか、はっきりするということなのでしょうか。
どちらにしろ、自分の方向性を決めていく上で、美空ひばりさんの存在を
しっかりと自分の中で整理しないといけなくなったように感じます。
でも、ここまで凄いものを見せられると、
一体自分に何が出来るのかと投げ出したくなりますので、
もう少し美空ひばりさんという歌手について考察していきたいと思います。(1019)
▲トップへ戻る 【美空ひばり「武道館ライブ」】
#013.
EDITH PIAF
シャンソンの「アコーディオン弾き」、これはストーリー性に富んでいます。
「街の女の彼女はとても美人だった」から始まるように、
まず歌い手のスタンスは『語り手』として登場します。
歌というのは自分がなり切り歌うものと、こんな物語、こんな物語というように
第三者的に歌い上げるものがあります。これは、語り手から入ります。
歌が進むにつれ、ストーリーが進んで行きます。
彼女の彼氏はアコーディオン弾きだった
ふたりはとても楽しいときをすごす
しかし彼は兵隊にとられた
彼女は彼が帰る日を夢見る
結局、彼は死んでしまった
彼女は彼の演奏していたホールにふらふらといくと
そこでは別の人がアコーディオンを弾いていた
彼女はアコーディオンにあわせて踊る
蘇る想い出
アコーディオンの音
帰らない彼
蘇る想い出
アコーディオンの音
帰らない彼……
蘇る想い出
アコーディオンの音……
『止めて』と彼女は叫ぶ、音楽を止めてと…。
この『止めて』のとき、ピアフは頭を抱え、顔をゆがめて、叫んでいる。
歌詞のストーリーが進むのにしたがって、ピアフもまた、
どんどん『語り手』を離れ『彼女』に同化していっています。
自分のものにしているわけです。
そして『止めて』のとき、完全に『語り手』ではなく、
叫び声をあげる『彼女』になっているのです。
だから、アコーディオン弾きの歌ではなく、ピアフの歌なわけです。
この歌にまつわるエピソードを一つ。
来日の際、ミルバが『ピアフ』をテーマにとりあげました。
この『アコーディオン弾き』も歌った。でも、ほんの一部だけ。
『止めて』の前までをすべてインストゥルメンタルで演奏し、
そのときミルバは舞台にはいない。そして、
ミルバは突然飛び出してくると『止めて』と叫び、以下を歌うという構成。
でも『止めて』とミルバが叫ぶと、ほとんどの客は笑った。
確かに、ミルバはいつも乗らない日本の客を喜ばすように、
ユーモラスな行動をとっていた。
多くの客はこの『アコーディオン弾き』の歌詞を知らなかったかもしれない。
だけど、何かがひっかかった。
『もしピアフが、同じことをしたとしたら?』
私は、客は笑わなかった、笑えなかった気がした。
ピアフとミルバ、何が違うのか。
ミルバの歌とピアフの叫びはやはり、対極的なものかもしれない。
ミルバはうまい、疑いもなくうまい。
しかし、ピアフはこの歌で『止めて』を叫ぶとき、その体に鳥肌をたてている。
全身が苦しみにもだえている。臓器をひきしぼって生まれてきた声だ。
ピアフにはアコーディオン弾きの恋人はいなかった。それなのに、
なぜ、ピアフは『彼女』になりきれるのでしょうか?
まるで、ピアフの恋人がなくなったように…。
ステージで、その「止めて」の一言は、
なり切ったのではなく、なっているわけです。
ピアフは「俺の靴に足を入れてみろ」というところにまで入れているわけです。
ピアフ自身が叫び、呼びかけているのです。(K)
▲トップへ戻る 【VTR エディットピアフ「アコーディオン弾き」】
#014.
DOMENICO MODUGNO
彼は「ヴォラーレ」を聞いて想像していた通りの人だった。
スケールの大きな感じの声に似つかわしいヒゲを生やした陽気なおじさん。
初めて画面を通してみた彼は、そんな表現がピッタリだった。
ステージやセットなどが、前に見たジャンニ・モランディのものと似ていたので、
きっと同じ頃なのだろう。 この頃の映像は、
イタリアらしい陽気な感じと、遊びゴコロがあって見ていて面白い。
でも、やはり驚いてしまうのが、彼らの声のすごさだ。
話していると思ったらいつの間にか歌っていたり、
高音の部分になっても声が太いままなので、
ヘンにカッコつけて「歌をうたう」というのではなく、
自然に歌をうたっていると感じる。
しかも、メロディがきれいでスケールが大きいので、
聴いていて思わず感嘆の声が出てしまう。
ライブステージでは、彼の力強さと陽気さ、
そして大人のあたたかさのようなものが滲み出ていた。
個人的にも、彼のような太くてストレートな声質が好きだと感じた。(N)
▲トップへ戻る 【VTR 「ドメニコ・モドューニョ」ライブコンサート】
#015.
FILIPPA GIORDANO
自分がやりたいことがはっきりしていれば、まったく前例のないことでも、
何をすべきかがわかり、辛いけれど迷いがないのだろう。
オペラ歌手の両親を持ち、発声の基本も身につけたところで、
そちらの道でも通用したかもしれないが、自分のやりたいことにこだわり、
やり遂げた精神に共感し、勇気づけられた。
「ポピュラー歌手だけによるオペラ上演の実現」という
“野心的な夢”を持っているが、肩に力は入っていなくて、
「大切なのは音楽を聞き手に届けること」
「音楽にはジャンルの垣根はない」
という信念をしぜんと実行している姿が魅力的だ。
声はくせのない、透明感のある声で、
高音ものびやかに、自在に歌う姿は妖精のよう。
声自体が太くて迫力があるわけではないが、
一曲の中でピークに向かって密度が上がる緊迫感は、
胸にせまり、説得力がある。
クラシックの基本があるうえで、響かせるより、
フレーズの流れで聞かせどころを作っていくような
ポピュラー的な歌い方を選択しているので、
声は完全にコントロールされていて、表現に幅がある。
その表現の幅の豊かさを一番感じたのは、カルメンの「ハバネラ」である。
ジプシーの匂いはしないが、可憐な小悪魔という感じで、
ぐいぐい引き込んでいく。
始めのうちは、まるで声で遊んでいるかのような軽やかさ、
自在な変化でカルメンの気ままさを表現し、
しだいに全く違うドスのきいたような声で「決め」のセリフを完全に演じきる。
一曲の中での表現力、バラエティの豊かさに、本当に驚いた。
ヤーヤ・リン指揮のスーパーワールドオーケストラの演奏も、
音が軽やかで、リズムが生き生きしているように聞こえた。
特にホルンとピッコロの音が新鮮に聞こえた。(O)
▲トップへ戻る 【フィリッパ・ジョルダーノ
コンサート】
#016.
JIM MORISON
何て強烈な個性の持ち主なのだ。
打ち上げ花火というより爆弾のような人だ。
人間は、本能のまま生きようとすればするほど、早死にするのではないかと思う。
日本は世界一の長寿国と言われているが、人間の本能からみたら、
一番遠いところで生きている気がする。
ジム・モリソンの生き方は、見方によればものすごく破滅的だけど、
決して死に急いだわけではないと思う。
人間が死ぬということは悲しいことではない。
死というものに目をつぶって生きれば生きるほど、色のない人生を送ることになる。
多くの人間は、死を見据えてまっすぐ歩いていくことなどできないだろう。
死が恐ろしいものなら生きることも恐ろしいものとなる。
彼がこの世に残していったものは、作品というよりその中に宿っている命。
一人の人間から多くの命が生み出される。
そして、その命を多くの人間が受け継いでいく。
命を生み出せる人間こそ、真の表現者だと思う。
何百、何千の命を生み出すなんてことは、普通の人間にはできることじゃない。
ステージを見ていて、DOORSのジム・モリソンというより、
ジム・モリソンのDOORSという気がした。
バンドの人には悪いが、ジムの存在にかすんでしまっていた。
ジムは自分らしくありたいというより、人間らしくありたかったのだと思う。
ステージの上で叫び、ささやき、好きなように踊るジムをみてそう感じた。
それは、ステージに上がる前につくるものではなく、
ステージの上で生まれるものだろう。その瞬間にしか生まれ出ないもの。
音楽はつくり出すというより、生まれ出てくるものだと思う。
心の奥底からわき出てくるさまざまな感情を吐き出す世界。
それは、絵だろうと小説だろうと彫刻だろうと同じかもしれないが、
音楽ほど直接的ではないと思う。
視覚よりも聴覚、味覚、触覚の方が人間の本能に、
より直接的に働きかけてくるのだと思う。
音の世界は、そこに入り込んでいけばいくほど、危険な面がある。
自分の肉体がなくなって、意識という形のないものしか感じられない精神状態になる。
ミュージシャンがドラッグの世界に入りこんでいくのもわかる気がする。
世の中のいい悪いの基準は、すべて社会にとってのもので、
人間の本能を基準にしたら違うものになると思う。
表現の場は、人間が人間に還ることのできる唯一の場だ。
この世に芸術というものがなかったら、人間は生きていないかもしれない。
人間に戻りたい、本能のまま生きたいという強い欲求がある人間だけが、
表現の世界を選ぶのだと思う。
ジム・モリソンの生き方は、ステージの上も下もない。
どこにいようと彼は彼らしく、人間らしく生きたいと願ったのだろう。
▲トップへ戻る 【DOORSコンサート
「ジム・モリソン」】
#017.
BILLY HOLIDAY
彼女がひたすらにこだわり、守り続けた芸術性とは…?
実際に、ビデオでビリー・ホリデイの声を聴くと、年齢によって、
また曲によって、その印象が違って聞こえ、明らかに感じたのは、
私の想像外の世界だったことだ。私の想像できたどんな声、表現でもない。
ビデオの初めに登場したビリーは、既に晩年らしく、
声はかなりハスキーで少し統一感がないように感じられたが、
圧倒的な個性でぐっとひきつけられた。
ゆったりと体をSWINGさせるように歌う姿、独特の表現のタイミングが、
美空ひばりととても似ているような気がした。
ビリーの歌の解放、感情ののせ方は、
“悲しそうに”とか“嬉しそうに”聴こえる…という単純なものではない。
声の音色とフレージングの何ともいえないタイミング
(ふんわり聴こえるけれど、確かにメリハリが効いていて
“アタックしている”感じが伝わってくる)が、その歌詞の意味を、
そして、何よりも彼女の目が語りかけてくる。
本でも“Strange Fruits”について触れていて、聴いてみたいと思っていた。
今回、実際に聴くと、本当に、本当にすごい歌で、身動きができなかった。
苦しくてつらかった。これは、歌なんだろうか!?
いったい何なんだ、ビリーの創り出す世界は…。
歌だけが飛び出ているような「歌」ではない、声でも、メロディでも、歌詞でもない。
すべてが彼女のメッセージとして全体を創っている。
いわゆる、歌に対する固定観念をぶち壊すものだ。
ルイ・アームストロングの歌もそうだが、ビリーの歌は、
やはり女性の内面に潜むものがベースにあって、
一人の人間としての強烈な個性を生み出しているように思った。
こういう歌い方ができれば、他のどんなやり方もできるんじゃないか…とも思えてくる。
楽譜の音符通りにしか歌えなければ、とても表現なんて域にまではいけないだろう。
彼女の生い立ちを考えると、彼女が歌にスッと入り込んでしまう気持ちは、
理解できる気がする(想像できる)。
彼女は、歌の中でだけは、たくさんのへこんでしまった部分を
満たすことができた…というか、彼女が受けた傷を癒せる世界、
唯一、自分自身とコントロールできた場が歌だったのではないかと思う。
彼女について知るほどに、そのバックにあるものの大きさを思わずには
いられないのだが、人の前に立つとき、彼女のバックボーンは、
深く集中されたサービス精神となって送り出されるのだろう。
1日で人の100日分を生き、常に最高のものを伝えたいという彼女の姿は、
真のアーティストだと思った。
彼女の歌は、どんなにスローにテンポをとっても、ソフトな曲であっても、
声そのものにプッシュ力があって、すごい底力を感じさせられる。
とにかく、声が耳に飛び込んでくる。本当に「迫ってくるもの」がある。
「一銭の価値もない曲も、ビリーが歌うと一級品になる」
この力、表現こそが、人々が求めるものだと痛感させられることばだった。
▲トップへ戻る 【「ビリーホリディ」
コンサート】
#018. LOUIS
ARMSTRONG
あの独特の太くて深くてしわがれた声。
彼はトランペットも同じように力強く吹き、吹きながら歌い、歌ってはまた吹く。
彼は話してもメッセージが伝わるけれど、
あの素晴らしいリズム感にのって歌い吹くことで、人々を感動へと導く。
これこそが、歌うことの意味だと思った。
華麗なキャリアの裏では、常に人種差別を感じ、それでも卑屈にならなかった。
そうなることは負けだと知っていたからだろう。
自分の気持ちはすべて黒人の気持ち…そう信じて、
彼は笑顔で肌の色を超え、黒人ジャズの素晴らしさを認めさせていったのだ。
何よりも一番苦しみ、そして、楽しんでいたのがルイだったからこそ、
聴く人々すべてに影響を与えられたのだろう。
自分がこれから歌っていくとき、どんなメッセージをもって歌っていくのだろう。
日々、強く繊細な心で世の中を知ること、
そして、人間に関わって生きていくことで、
何かが得られるかもしれないと感じた。(T)
▲トップへ戻る 【「サッチモ」ライブVTR】
#019.
MARLENE DIETRICH
歌をやりたいという以前に、一人の人間として立ちたかった。
男とか女とかそんな枠で考えるのではなく、
一人の人間として自分にしかできない表現をしたかった。
自分の考えを、自分の声と言葉で言いたかった。
そんな思いを、彼女をみて思い出した。
マレーネ・ディートリッヒのステージは本当にシンプルだ。
彼女だけがそこに立ち、語り、歌っている。
それで成り立っているし、観客も喜んでいる。
観客は総立ちしたりしないし、興奮を表わしたりはしないけど、
皆が本物は何かということを知っているようだった。
こういうステージをみてしまうと、日本人はどんな文化をつくってきたのだろうと
考えてしまう。世界がこんなに近くなっても、よいものがなかなか入ってこない。
メディアをつくっている人たちは、よいものを本物を知っているのだろうか。
やはり自分の足で探さなければよいものはみつからないのだろうか。
なんだかとてもうらやましくなった。本物を支える層の厚さに。
どうにかしてこの日本も、そういう大人のたくさんいる国にしていきたいと思う。
それには自分の力をつけるしか道はない。
彼女の表現、声は彼女のものだ。決してハッとさせられる声ではないのだけれど、
話し方や表情が声と合っていて、聴いていて心地がいい。
派手な動きなんて全然ないのだけれど、
ちょっとした目の動きやジェスチャーにひきつけられる。
そして、とてもしっかりとした声を出している。
その声に感情をこめ自由自在に語っていた。
歌っているようには聞こえなかった。すべての歌が語られていた。
一流の人の歌を聴いていると、日本人が歌っているような歌い方をしている人は
いない。声を聴いていると、いつの間にか曲が消えていってしまう。
そして、語りかけられているような感じになる。
深い息に支えられた声で言葉をいっているだけなんだと思う。
彼女のすごいところは、一つひとつの歌にすぐ入っていけるということ。
悲しい歌、喜びの歌、嘆きの歌といろいろあるが、
彼女自身、その歌の世界に入りこんでいく。観客もその世界にひきこまれていく。
飽きさせない、ひきつけられるものがそこにある。
存在感のある人だ。(K)
▲トップへ戻る 【「アンイブニングウィズ」マレーネ・ディートリッヒ】
#020. BOB MARLEY
レゲエの歌詞をいろいろみたら、曲の感じとは全然違って、
世の中の理不尽なことや心の苦しみ、哀しみそんなものが多かった。
生活に根づいた音楽、時代に根づいた音楽。
日本からはこういった音楽は決して生まれないだろうと思ってしまう。
ボブ・マーリィは自分の求めているものをちゃんとわかっていた人では
ないだろうか。どういう生活をしたくて、どんな歌を歌いたくて、どう生きたいかを。
環境の影響もあって選択できるものが少なかったということもあるかもしれない
けれど、多かろうが少なかろうが自分を知っている人は選んでいける。
今、世界のレベルで通用する声を手に入れたいと思っているわけだが、
かりに手に入れても、ショーウィンドウに飾ってあるだけのものになってはいけない。
世界の音楽を知ることは、今、この時代に日本とは違う国がたくさんあり、
そこで人々はどういった生活をし、何を考えて生きているのかを知ることに等しい。
たとえそこに行けなくても、人間には創造する力があるのだから、
それを活かせばいい。だけどこの身体が動くならば、
いろんな国の空気を人々を肌で感じたいと思う。
日本の歌って、日本の心ってなんだろう。
日本は何百年も前に鎖国をといたはずなのに、
人々の心は今でも鎖国状態のような気がしてしようがない。
人間を育てていかない、感動をひきおこさない歌が多すぎる。
日本しか知らず(知ろうとせず)、小さい枠の中だけで歌いたくない。
日本の中だけで歌うとしても、私の心の中にはもっと大きなものをつめこんで
歌いたい。ちっぽけな人間ではいたくない。
ボブ・マーリィの瞳がものすごくきれいでいいなぁと思った。
目の中に心のきれいさがあらわせていた。まっすぐをみつめる瞳。
バンドマンは「今の生活からぬけでるにはプロデューサーに認められるしか
ないんだ」といって、曲をつくっては聴いてもらうことの繰り返し。
この日本にいると何のために自分は歌い、誰にむけて歌うのか、
どんな歌を?と常に考えさせられる。
生活に何の不自由もなく、あっても大したことなく、
明日生きてるか死んでいるかなんてことは考えることもなく、
腹をすかしても死ぬわけではないこの国で、何を歌うのか。
私は何も知らない、わかっていないに等しい。
だから日本を世界を知りたいと思うし、わかりたいと思う。(K)
▲トップへ戻る 【ザ ボブ・マーリィ
ストーリー】
#021.
CHARLES TRENET
「表現の裏にあるもの」
彼のビデオを見て、なぜこの人を見てると楽しくなってしまうのだろう、
ウキウキしてくるのだろうと思った。
足をガンガン踏みならしながら思い切り拍手したい気分だった。
特に「喜びあり」を聴いたときは、全身の血がざわざわしてくる感じがした。
まるで、この世につらいことなど存在しないかのように、
存在したとしても、そんなことでくよくよするのなんか馬鹿げてるよ、
とでも言うように、彼は瞳をかっと見開いて生きる歓びを歌う。
この人、悲しい思いをしたことないのか?
なぜまわりの人すべてを幸せの中に巻き込んでしまえるのだろう?
と、その秘密をどうしても知りたくなった。推測するに、
彼は本当はすっごくシリアスに、ものごとを受けとめる人なんじゃないかと思う。
表現になるのは、彼の陽気な部分だけだが、
彼の内面はとてもシリアスなのでは?と、彼がビデオの最後の方で
歌った歌を聴いて、強く思った。
歌の題名も歌詞もほとんど忘れてしまったが、
“死んだら、空腹は終わり。蚊にさされることもない。幸せと自由が待っている。”
といったような詞の内容だったと思う。
こういう歌を歌えるのは、夢を見るすき間もない現実に身をおいて、
その苦しみを存分に味わい、死をも考えたことがある人だけだ。
ただのノーテンキ人間が歌ったら、きっと「他人の苦しみも知らないくせに」と
思ってしまう。彼はノーテンキではない。
逃れることのできない現実や死というものをきちんと踏まえた上で、
それでもやっぱりというか、だからこそ、夢を歌うのだ。
つらいことが多いからこそ、生きることの歓びの部分を
体いっぱいに受けとめ、表現するのだ。
表現というのは、彼のように表面上に見える部分を裏づける陰の部分が
すごくしっかり確立されていないと、人の心を打たないし、
第一、表現する必要性がないように思う。
表現者は、一見相反するようなものの見方を両方理解し、
「うん、でもやっぱり、こうありたいよね…」の部分を表現するものじゃないか。
というか、自分の中で相反する考え方、両方に共感してしまったゆえに、
もがき苦しんで、なんとか答えを見つけたくて、なんとか自分の立場を確認したくて、
表現さぜるを得なかったという流れで、何かが生まれてくるのではないか。
▲トップへ戻る 【「ラ・メール」シャルル・トレネ】
#022. TOM WAITS
歌とは何だろう。芸術とは何だろう。
改めて考えていた。
深い霧が降りてくるように、不思議な空間をつくるトム・ウェイツの音楽。
いかに自身を見つめ確立し、深い世界観をつくっているかが見えてくる。
1949年、カリフォルニアで生まれる。
ブルース、ジャズ、ビートニクの時代に影響を受けた青年時代。
70年代のデビュー以来、独特のしゃがれた声と
たくさんのストーリーを語る「酔いどれ詩人」、
前衛的アーティストとして注目を浴び続けている。
また、面白おかしいジョークも彼の舞台の魅力のひとつである。
俳優としても活躍し、フランシス・コッポラや
ジム・ジャームッシュ監督たちの映画にも個性的な演技を披露。
名曲「OL55」「ダウンタウントレイン」は、数多くの音楽家たちがカバーしている。
近年は、演劇舞台の音楽も手がけるなど、幅広くその才能を発揮している。
酔って砕けたようなピアノやギター、潰れ濁った歌声が独特のストーリーを語る。
味たっぷりにそれらが溶け合い見事な空間をつくる。
深く熱いパッションの持ち主である。
とくに本人のバラードは傷を癒すように心地よく、そして切ない。
地球のどこか、まったく離れた場所でまったく違う人生を送る一人の人間の歌に、
自分の幸せや悲しみが重なったり、共感を覚えること、
大きな力を感じることが不思議でならない。
そしてまた、それが芸術の魅力であり、
心の力であることが偉大なアーティストを通して教えられた。(Z)
▲トップへ戻る 【「LIVE STORY TELLER 1999」】
#023. ELVIS PRESLEY
アメリカで最も有名なスターの一人であるエルヴィス・プレスリー。
ロック、ポピュラー音楽の歴史、文化に大きな影響を与え、
重要な役割を果たした。反抗する若者を象徴した時代のロックンローラーから
エンタテーナー的アイドル、俳優として一気に人生を駆け抜けていった。
1935年、ミシシッピー州に生まれる。
幼年時代から教会の聖歌隊の一員としてゴスペルを歌っていた。
人種差別がひどい時代の流れに反して、黒人のブルース、R&Bに
魅せられていく。青年時代には工場やトラックの運転手として働きながら、
黒人が使うポマードをつけ、彼らのファッションをまね、
ギターをもって、当時ブラックカルチャーのメンフィスの歓楽街を徘徊した。
50年代に白人でR&Bが歌える歌手を探していたプロデューサーの目にとまり、
プロとしての人生が始まる。反抗する若者を象徴する彼の存在は、
同世代の白人青年たちを惹きつけ、一気にアイドル的存在となっていく。
しかし、そのスタイルや腰を振る姿に、白人でありながら、
黒人の文化に取り憑かれていると、大人たちから叩かれていた。
そのような状況に、一時期は当初のエルヴィスにテレビ局も消極的であったものの、
あまりに多くの若者たちに熱狂的に支持をされ、やがてロックンロールは、
白人社会にひとつの文化として定着していく。
多くのヒットソングを出し、熱いタフガイなイメージがアメリカ中の
女の子たちを惹きつけ、いつしかアメリカのマスコット的な存在、
エンターテーナーとして華やかなショービジネスの世界を歩んでいく。
時に派手すぎるくらい明るく、パワフルでドラマチックな歌い節、
太い豊かな熱い声。
アメリカ人がもつ特有の雰囲気や気質が、彼の声から思い浮かんでくる。
アイドルとして、エンターテーナーとして商業的な音楽業界に操られ、
ハムのようにされながらも、幼年期に黒人の音楽にあこがれていた
隔たりのない純粋な思いが歌の奥につねに潜んでいる。
120パーセントの超人的な体力とパワーで飛ばしに飛ばした人生。
42歳の若さで他界してしまったが、
まるで90歳くらいまで生きたかのような強烈な印象をこの世に残した。(E)
▲トップへ戻る
【プレスリー「DVDドキュメンタリー」】
#024.
CHARLIE CHAPLIN
人を愛し、人生を愛し、世界に光を与えた、喜劇王 チャーリー・チャップリン。
映像は何時見ても、斬新で人に深い幸せを与える。
ドキュメンタリーは究極の芸術を苦闘し追及し続けた巨匠の形跡を追う。
19世紀末、イギリス・ロンドンの貧民街で生まれた彼は、
いつも口の中に小石を入れて、ひもじさに耐えていた。
「ぼろをまとっていても上品でありなさい。」
かつて役者であった母親から、チャップリンはパントマイムや演技を自然と学んだ。
貧しいが幸せな一家であった。しかし14歳のとき、母親が精神病院に入院。
劇団に入りパントマイム、演技を鍛え磨きながら家庭を支えた。そしてアメリカへ渡る。
どんな世界にも響かせられるためにと、言葉を使わずサイレントにこだわった。
多くの名作をつくっていく中、転ぶシーン、歩くシーンなど一つ一つの動作から、
綱渡りなどの困難なシーンまで、何度も時間をかけ工夫をこらし、
厳しく自分が納得いくまで練習をし、撮り続けた。
機械中心の社会で多くの労働者の心身が病んでいくのを描いた「モダンタイムス」。
迫力の問題作「独裁者」は、大戦中に製作に脅しをかけられながらも、
ヒトラーのあらゆる映像から彼の動作や演説を研究し、
立ち向かうために声を入れて完成させる。
しかし、映画は不評を受け上映禁止となり、国外追放に。
1970年になるまで、アメリカに戻れることはできなかった。
そして77年に88歳で亡くなるまで、作品を意欲的につくり続けた。
進歩のない同じ過ちを繰り返す人間の社会。
「独裁者」でチャップリンが残したメッセージは、時代も国境も超え語りかけてくる。
「人類は互いに助け合うべきです。
他人の不幸ではなく、幸福によって生きたいのです。
悩みあってはいけません。地球は豊かで全人類を養うことができる。
人生は自由で美しいはずなのに、私たちは道を見失いました。
貧欲が人の魂を毒し、憎しみをもたらし、悲劇と流血をもたらした。
独裁を排し、自由のために戦おう。神の国は人間の中にある。
すべての人間の中に。みんなの中に。あなた方は幸福を生み出す力を持っている。
人生は美しく、自由であり、素晴らしいものだ。」(A)
▲トップへ戻る
【チャップリン「DVDドキュメンタリー」】
#025. STEVIE WONDER
“多くの人が過去の時代に生きている。
人種差別がまだ容認されるような時代に差別を受け入れて邪悪を信じている。
それを祭りあげて生きている。
しかし、また一方では未来の楽園を夢みる人々がいる。
人類が一つになるという時代や精神に生きている。
予言が実現するのを待っているんだ。”
限界のない表現者。独特のリズム、メロディーメーカー。そして、詩。
自分の感覚を鋭く巧みに扱う。瞬間的に入ってくるものを受け入れ、吸収する。
ルールに毒されることなく、その自由な発想は、体のままに、感じるままに、
歌になり世界へのメッセージとなる。
1950年、アメリカのミシガン州の小さな村に生まれる。
12才からプロとして今も活躍。このDVDでは70年代に作られた名作アルバム
“Songs In The Key of Life”の制作当時を本人と周りの関係者たちが振り返り語る。
“見える者より多くのものを見ている”と、共演者の一人。
自分たちには見えない神と関わる何かをもっているようだと言う。
作曲し、演奏し、歌い、プロデュースする。
コンセプトをしっかり先まで見つめるその姿勢には、過去だけでなく、
音楽の未来の行方が見えるのかもしれない。
そして、つねに社会を心で直視する。
“与えもせず、ものに溺れるどん欲な人々もいる。”
“人が与える最高のものは時間だ。
その渦中にあるときはあまりに入り込みすぎて、その時間の大切さに気づかない。
学べば学ぶほど、自分の行いに責任を持たなくてはならない。”
ジャズの巨匠デューク・エディントンに捧げた曲‘Sir Duke'について
彼はエディントンの残した言葉を大切にしている。
“最高の歌は未来にある。できることは無限大。
しかし、経験した時間と空間は忘れることはない。”
その言葉のとおり、今も色褪せることなく精力的に作品を作り続ける。
視覚ばかりを重視し、唯物化していく灰色の社会の中で、
前向きに生きる本人の輝きは衰えることなく、
人々に目には見えない確かな力を与え続けている。(M)
▲トップへ戻る
【DVD
「Songs In The Key of Life」】
#026.MERCEDES
SOSA
愛、そして勇気。そのまっすぐな愛情を社会へぶつける。
「大地の歌声 ラテンアメリカの母」と呼ばれる。
中南米の伝統音楽フォルクローレや、反戦歌を歌う、
ラテンアメリカを代表する女性歌手。
1935年、アルゼンチン北部の山岳地帯の村で生まれる。
祖国の自然、広大な大地を吹き抜けていく風の中を、
恐れず裸足でしっかりと立っている人間像を思い浮かべる生命力
あふれる力強い歌声。そこには幼き頃の変わらなき純粋な光が宿っている。
自然の恵み、命を受けた尊さが呼吸と共に聞こえ聞く者の心を震わす。
愛の歌、夢の歌、そして反戦歌。
当時のアルゼンチンの独裁政治の抑圧に苦しみ、
生死を彷徨う人々のため、命をかけて自由と人権の尊さを歌う。
映像では、歌を通して、インタビューで繰り返し彼女が語る言葉がある。
−エスペランサー希望−
人間としての基本的な善悪の判断をせずに歌を歌っても何の意味もない、
平和、正義、そして自由という同じ理想が私たちを一つに結ぶと言う。
残酷で痛ましい社会状況に正面から向い闘い続けている。
映像からは目を輝かし、希望を持って一緒に歌い出す人々の姿が伺える。
彼女の歌は、人々が手を互いにとりあい、思いやること、空を見上げるように
目を見開いて生きることへ力を与え、問いかけている。
彼女の声を聞くと自分が再び赤子に返るような感覚を与えられる。
それはつねにある深いところへ、海の中へ導くかのようだ。
感動して止まない真の芸術、歌という力、表現が彼女の中にある。
それは、軽率に判断されることのない、心の奥底からくる、消えることも、
逃げることも、奪われることもない純粋さが働きかける。
彼女の歌声は、さまざまな世代、境遇におかれる人々を全身全霊で包み込む、
偉大なる社会の母の叫びである。(A)
▲トップへ戻る
【メルセデスソーサDVD
「Live&Interview」】
#027.SHINRO
OTAKE
芸術は果てしなく難しい見えないものを見えるものにする作業。
求めるものの深さ、そして自由を知れば知るほど、
この社会の中で、個々が生む芸術の意味、責任や試練も大きい。
作者の心の問いかけ、迷い、その半生の旅を見た気がする。
隙間もなく紙面上を埋め尽くし、塗りつぶしていく、大竹氏のコラージュ。
少年時代から変わらず無意識と意識の中で、
たんたんと貼る作業をしてきたという氏の膨大な作品の数々を見ていると、
混沌と織り交ざる多文化と流れるような膨大な情報、支配や暴力、
新しいビル、新しい街、満員電車、店から流れる1920’s ディクシージャズ。
信号で止まる車からは大音量で日本のラップが聞こえてくる日常、
そんな今日の日本のジャングル社会がリアルに表されているように思える。
そしてそんな環境の中で生きている自分たちなのだと改めて考えさせられる。
“りっぱなほりものを作り上げて、そのほりものを世界一のほりものに作り上げたい。
あまりみごとなほりものなのでそれがまるで生きているようなりっぱなほりものを
ほりあげて、日本のぼくのほりものが世界的に有名的に有名になりたい。”
小学校の頃の大竹氏の作文。絵や工作に夢中だった少年時代、
西洋の文化がますます入り高度成長期真っ只中の60、70年代。
大竹氏の作品もまさに、それらに強い影響を受けていた。
しかし、デビュー後、ナイロビなどへ旅をした頃から、
作品にも視野が広がっていくのがうかがえる。ラインや色使い、温度が変わりだした。
旅の後、展覧会などせず黙々と作品を作っていた3年間の空白の中の作品。
「東京プエトリコ」や「ゴミ男」は、都会の殺伐さ、エゴやうめきなど暗闇や欲望、
そして脱出できない人間の空しさがにじみ出ている。
再び長い旅を経て、描いた作品集「網膜」には
本格的に精神世界を分解して見始める姿がうかがえる。
“血の記憶”“極氷”“火傷”など、その色彩力、コンポジションなど
抽象的な鋭い感覚が自然の神秘をキャンバスによびおこすような作品が続く。
長い時間をかけて自分との対話、世界との対話の中で、
ようやく何かが表現しはじめたようにも思える。
その後の作品集「アメリカ」でもそれまでの日本に入ってくる流行文化や
あこがれを描いていたのとは異なり、国の現実を繊細な彩りで描いている。
同じく、そのような状況をシニカルとユーモアを混ぜ奇抜な色使いで描く「日本景」。
「もじゃおじさん」「んぐまーま」など子供の絵本も作り、
自由に崩したラインでユーモアな楽しい主人公たちを描く作品もこの頃から始まる。
2006年の新作「釣船」は、30年間本人が心の中に見てきたこと、
子供の頃を思い、子供への愛情が織り交ぜられているように見える。
芸術家は道なき道を行く。
この社会の中で生まれ、和が薄まり、洋に囲まれた生活環境、多くを気づき、
真の芸術を求めれば、気づくことは、この無限の地の上で、道なき道を歩いている。
一人の芸術家の半生にわたる作品を通して、自分自身の足元を見つめ返していた。
▲トップへ戻る
【大竹伸朗展】
#028.TORU
TAKEMITSU
作るのではなく、聞こえてくる音を取り出すという考え、
命や自然を聴くということに生涯をかけ、彼にしか聞こえない音、
発見できない音、宇宙の音と評されるほどの独創的な音楽観、
作品で、世界的に音楽界に新たな大きな発見と衝撃を与えた作曲家。
「戦争が終わったら、僕は音楽家になろう」
終戦後、手探りで作曲を学ぶ。紙にピアノの鍵盤を書き、練習をした。
クラシック、ロック、ポップ、隔たりなく様々な音楽を聴き、
様々な演奏家たちと交流をした。
西洋の音楽に違和感も覚える中、やがて地にはり、空へ伸びる樹の命に魅かれ、
大きなインスピレーションを受け、自然の中で暮らし始める。
そこから得た発想を音符やスケッチにした「樹の曲」「雨の樹」など、
樹の曲を数々と作曲する。
自然の美しさを尊重した日本の庭にまつわる曲もたくさん残す。
「秋庭歌」など、日本的であり、宇宙の神秘さ、美しさを音による庭として表現した。
「海の音楽をつくりたい」
晩年は、幾層もの上流を包み込む海という、
西洋と東洋の発想というのを越えたところで作曲。
「waterways」は、各楽器は夜の海をそれぞれの水路にそって進み、
やがて小さな支流は合流して調性の海へ進むという壮大なスケールで書き上げた。
「地上の異なる地域を結ぶ海と千変万化する豊かな表情に
次第に心を奪われるようになった。
できれば、鯨のように優雅で頑健な肉体をもち、西も東もない海を泳ぎたい」
音楽が体を貫いて世界と輪になってつながっていく曲集「海へ」。
各地から流れてくる波や風のような旋律は心の振動を覚え、
宇宙、生命のつながりを感じさせる。
全て同じ命。それを音でつなげていく。
深い探究心、叡智に満ちた偉大な芸術家である。
▲トップへ戻る
【Part
I 「TVドキュメンタリー武満徹」】
#029.
VIOLETA
PARRA
“すべての人の歌 それが私自身の歌 人生よ、ありがとう”
ラテンアメリカ、チリを代表するシンガーソングライター
ビオレータ・パラの歌 “GRACIAS A LA VIDA”。
1964年、愛する人が去った絶望の中、自らの身を絶ってしまった彼女。
しかしこの歌は、その後不思議な運命を辿っていった。
ドキュメンタリーは、メキシコを代表する歌手アンバロ・オチョアの
娘である若手歌手、マリアス・イネア・オチョアが亡き母が愛したこの歌と
当時の足跡を追ってラテンアメリカを旅する。
さまざまな人々との出会いを通して、歌と母親が生きた激動の時代を知っていく。
80を過ぎた今も健在で歌い続けるビオレータ・パラの弟が語る
ラロ・パラの姉との思い出。
ビオレータの歌を愛し、社会主義を志した大統領アジェンテが、
1973年の軍事クーデターに倒される前に残した国民へのメッセージ。
ビオレータを敬愛していた吟遊詩人、歌手ビクトル・ハラが虐殺される
前に書いた最後の詩と、それを読む奥さんの姿。
囚われ痛めつけられながらも生き延びた3人の女性たちの涙。
拉致され行方不明になったままの家族を探し、街中に立ち続ける人々。
そして余儀なく国外追放されていたアルゼンチンを代表する歌手メルセデス・ソーサ。
当時の様子を話し、この歌を歌う。一人一人の姿と声が訴えかけてくる。
悲惨な歴史の中で、歌は、人々の強い願いと愛情の中で生き続けている。
“今も真実が知りたいし、正義が見たい。”冬の街中で家族の写真を抱えながら
待ち続ける老婆の言葉。そして、行き交う人々が口ずさむ。
“人混みの中から 愛する人を すべての人の歌 それが私自身の歌
人生よ、ありがとう” (A)
▲トップへ戻る
【ドキュメンタリー
世紀を刻んだ歌「GRACIAS A LA VIDA」】
#030.
AUDREY HEPBURN
若い時のヘップバーンは“妖精”という形容詞がピッタリである。
晩年に近い彼女は、気品ある一人の女性として、最も美しく見えた。
万人に愛され、綺麗なだけの人形ではなく、
意志や信念を持った大人の女性として行動した。
自分さえ良かったらいいという人達が多い世の中で、愛されるだけでなく、
愛することを行動に移した人間愛豊かなヘップバーンという人は、
やはり稀有な存在だろう。
そして、あのアンネの時代にアンネは死んで、彼女は生き残ったことを、
今回、初めて知って言葉に言い尽くせぬものを感じた。
あの時代のすべての哀しみを含めた暗さを、まるで、少しでも
埋め合わせするかの如く、神はオードリーという類まれな美しい天使を、
この地上に贈ったとでもいうのだろうか。
第二次世界大戦後、廃虚と化した人類に、うなだれ、打ちひしがれている人類に、
希望の光として…それは映画界から退いた後の彼女の生き方をみても、
単なる“個”としての人間でないことがわかる。
あれ程の美しい女性にも、美しいなりの、美しさに留まらない人間としての
“生きざま”があることを、私は観た。
そして、清々しい風が、胸の中を通りぬけていくのがわかった。
▲トップへ戻る
【「オードリー・ヘップバーン」映像】
#031.
SERGE
GAINSBOURG
入り口は少年ふうで、幼くもどこか一片だけ妙に成熟している。
ロリータ風のジェーン・バーキンが写っているジャケットがオシャレ。
これを見れば、ゲンスブールがカリスマ的存在であろうことは伺い知れる。
アメリカは娯楽で軽薄で、ヨーロッパの方が奥が深いという人も多いけれど。
アルバムの曲は、一枚でひとつのオムニバスというか、ストーリーになっている。
前面に表出されているのは、ギターの調べに載せて流れるゲンスブールの”語り”。
歌なのかもしれないけど、歌ではなくて、やっぱり“語り”。
”叫ぶ詩人の会”じゃなくて、”ささやく詩人の会”。
語りだけど、それにオーケストラがかぶさって、合唱がかぶさって、
それが鋭くて、油絵みたい、ミュージカルみたい、セルジュワールド。
やっぱしこゆい、深い、沼ってる・・・。
ジェーン・バーキンが、セルジュの「君の名は?」って問いかけに対して、
「メロディ」って答えるくだり、もう抱きしめたくなるくらい、かわいい。
ゲンスブールの人相も独特。イタリア語が、フレーズを持つ“音楽”なら、
フランス語は“詩”(愛撫)なのかなぁ? 英語はたて乗りの“リズム”?
日本語は“吟ずる”?・・・やーめた。
彼は詩心、構成力に加えて、BB(ブリジット・バルドー)や、バーキンを世に出す
プロデュース力があり、さらに音の構築(イメージ)の中に、“絵画感覚”がある。
コミック感覚もある。これがすごく世間の評価を長らく受けてるのか。
いやカルチャーショック、ヒット、いろいろアリやなあ・・・。
これくらいインパクトや、揺さぶり(なんかちゃうぞーっていうような違い)
新しいもの、刺激を与えてもらえると、値打ちがある。
インスピレーションがわく。
▲トップへ戻る
【セルジュ・ゲンスブール
「メロディ・ネルソンの物語」】
#032.
BILL EVANS
17世紀はクラシックもJAZZのように即興演奏が主だったが、
録音技術がなかったため、楽譜をどう解釈するかになり即興的側面はなくなった。
今やJAZZも同じ道をたどりだしている。JAZZを形式として考える人がいるからだ。
クラシックは1分の音楽を3ヶ月かけて作るが、JAZZは1分の音楽を2分で作る。
JAZZは瞬間的、自然発生的である。
やるべきことを認識し、それに没頭すれば結果はついてくる。
真実を三つ、何をどうするか明確にする。
事柄を明白にし、現実に直面し、それを分析する力を持つことが何より大切。
どの分野でも成功する者は、最初から現実を見る目を持ち、
困難に一歩づつ立ち向かい、学びの過程を楽しむ術を知っている。
慎重になりすぎたら何も発見できないから、冒険心は絶対必要だが、
それでも長い目で見れば、何が正確で何が不正確かを知るべきだし、
冒険の成果の可否も認識しなければならない。
制限がないところに自由はない。
ジャズを弾くために必要なことは、技術的に困難なところを
個別的に取り上げ、根気よく集中的に練習を重ねること。
それができたら、次の困難な場所に移る。
困難の理由さえわかれば克服の過程が楽しくなる。
ビル・エヴァンスが志しをたて、N.Y.に行った時、
ジャズで生計を立てるのはかなり難問だと思ったが、たとえ仕事がなくても、
とにかく弾き続けようというゴリ押ししない姿勢でやっていた。
自分の力を最高に発揮できる分野を選び、全力を尽くせば、
その力が他の分野に波及して全体がよくなる。
形式ではなく本質を学ぶ。
本当に学ぼうと思ったら自分で学ぶしかない。
自分の感性で取捨選択する。(O.K)
▲トップへ戻る
【ユニバーサル・マインド・オブ・ビル・エヴァンス】
#033.
JOHN COLTRANE
より高く光輝な場所へ、誰よりも高い山を登り続け、
遥か高く見えないところで消えた伝説のサックス奏者ジョン・コルトレーン。
時代の先の先を走り続け、誰にも創造できない世界を築きつづけた男の本性は、
好奇心に満ち溢れた極まりなく真面目で、最高の芸術のために全てを捧げていた。
1926年、ノースキャロライナに生まれ、熱狂的な礼拝音楽の中で育つ。
製糖工場に働きながら、音楽学校で勉強をし、1945年には海軍の中で
軍楽隊に所属。その後は、ガレズビー、パーカーたちのビーバップに影響を受け、
彼らから学びに学ぶ。サックスをサックスのように吹こうとしないスタイルは、
パーカーとよく似ていたといわれる。
気にかかる、分かりたいことは、全て分かろうとした勤勉家でもあり、
何万時間の練習の中、アフリカや東洋の思想、文化なども積極的に学び始めた。
誰もあれほど一生懸命ずっと練習する人はいないと言われるほど、
体が弱いにもかかわらず、ライヴの直前までも汗だくになるまで練習をしていた。
彼の革新的なスタイル。
常に両極端に分かれる評論の中で、聴衆もますます増えていった。
音楽は悟りの手段であって、目的ではなかった。精神的高まりへの過程。
やがて、ラヴィシャンカールとの出会いにより、古代の哲学をより深く学ぶ。
一連のパターンが作り出されある種の精神状態に入り、ヴァイブレーション、
それが世界の構造を理解する第一歩なのだと教えられる。
その中、彼の音楽はますます自由化していく。
極まりない技術や才能に恵まれ、周りがどんなに驚き絶賛しようとも、
彼自身は満足することはなかった。誰も着いていけなくなるほど前進していく。
前衛に突っ走り、多くのファンを失う。しかし、止まらず走り続ける。
その難解さに多くのファンを失いながらも、もっとフリーに、もっと究極な
インプロビゼーションを求めやめなかったのも、そこに果てしない信仰や信念があり、
より上へと求めた真の芸術家であったからこそだと思う。
その果てしない実績を築き上げたコルトレーンは、
今、生きる世界中の芸術家たちの師となり、走り続けている。
▲トップへ戻る 【ジョン・コルトレーン ドキュメンタリー】
#034.
TIKUZAN TAKAHASHI
名人・高橋竹山の演奏を聴けてよかった。「岩木」が一番好きだ。
曲の始めにベベン!と鳴らした時、うわぁすごい音だと思ったのが調弦だった。
張り詰めていて、澄んでいて深くて厳しい音。
竹山の人生があの音のような人生だったのだろうと思う。
竹山は明治43年青森県津軽地方平内町小秦生れ。
3才の時にはしかにかかり、ほとんど目が見えなくなった。
15才で戸田重次郎のもとへ弟子入りをして三味線と唄を習う。
当時は皆12、3才で色々なところへ弟子入りしていった。
竹山は、目が見えないから三味線をやるほかなかった。17才で独立。
師匠のもとを離れて一人で北海道、東北地方を三味線を弾いて歩く。
「つらいもんですよ」
雨の日は三味線の皮がはげてしまい弾くことができない。
だから尺八も覚えた。尺八は雨にも強い。
「下手でも吹いていれば音が出てきた」
尺八の演奏「津軽山唄」の音は、ヒィーという何か聴いていたくないような痛い音だ。
昔の人は、少し弾くとうまいじゃないか、かわいそうだからと一銭でもくれた。
戦争中は、なんで戦なのに喜んで三味線なんか弾いているんだと言われた。
「津軽中じょんがら節」はそういう辛い想い出とともにあるものだ。
「寝ていたって弾ける」門つけの旅は満州にまで及んだ。
昭和16年から始まった太平洋戦争。昭和20年8月6日広島に原爆投下。
9日に長崎に8月15日、終戦を知らせる玉音放送。この時代、竹山は34才。
戦争で三味線を続けられなくなり、新しい人生を始めようと盲学校へ入学。
鍼灸師の資格を取るためだった。
この頃、日本の伝統である民謡を保存していこうという運動が高まっていた。
その運動の東北地方代表の一人であり津軽民謡の大御所である成田雲竹に、
ぜひ弾いてくださいと声をかけられ、再び三味線を演奏するようになった。
竹山は成田雲竹野伴奏者として演奏旅行を共にする。
それまで三味線のなかった津軽民謡に三味線を手づけていった。
公演は日本だけにとどまらず、N.Y.やパリにも三味線を弾きに行った。
「津軽じょんがら節」「津軽よされ節」「津軽小原節」は、
合せて「三つものがたり」と呼ばれている。
師匠だった戸田重次郎から教わった。
心に残った「岩木」は、竹山自身がふるさとの自然や人生を思って作った曲だ。
ぼんやりと見えていた視界も暗くなり始めた50才のころだ。
そして、その後完全に視力を失ってしまう。
「目ェ見えなくっても気持ちでわかる。心でわかる」
竹山は少年の頃から夜越山で一人時を過ごすのが好きだった。
山の中で耳を澄ませていると、山の心理が分かる。
夜明け前の3時頃、木々の間から聞えるガサガサいう音は鳥が目を覚ました音。
川でパタパタパタパタいうのは鳥が水浴びしている音。
「黙って鳥の声を聴く。日暮れや夜が明けかかんとする山の雰囲気はいいもんだ」
竹山は演奏会の最後を必ずこの曲でしめくくる。
▲トップへ戻る 【高橋竹山 「その人生」】
#035.
JIMMY SCOOT
憂鬱だからといって、歌を口ずさむ心をなくさないで下さい。
音楽はこの世で最も大きな“いやし”の力なのです。
音楽には愛と思いやりが満ちているのです。
旋律の魅力だけでなく、人生の物語を感じさせる歌詞にひかれる。
そういった楽曲を、ジャズの様式に再構築して歌うのが僕の流儀なんだ。
人はリスペクトしあわなければ。
生きることの痛みや虐待から自由になるためには、許すしかなかった。
そうしなければ、自分の体が出す怒りや哀しみの毒薬で死んでしまうと思ったから。
手本があったわけではない。
魂の叫びを静かに表現する方法として、最初からずっとこのように歌っていた。
つらい経験があるからこそ、歌に潜む本質を探し出せ、
歌の真にいわんとすることを聞き手に伝えられる。
私が先生でわたしの音楽を聴いてもらえる人を生徒さんとすれば、
生徒さんには授業を通して満ち足りた人生を生きる勇気を
学び取って欲しいのです。
* *
*
― 顔が小さかろうが、体が小さくて、バンドの人と肩が組めなかろうが、
髪の毛がちぢれていようが、眉毛なかろうが、もう歳で歩く時に、
ヒザがちゃんと曲がらなくても、人間の魅力や人生には関係ナイのだ。
トリオの演奏時間がけっこうあり、いつもはぼんやり聞き逃してしまう、
サックスもふと(ああよい音だなあ)と思った。
バスの人が神経尖らして繊細に音を扱ってるのが分かった。
ある一定以上の年齢の人だけがかもし出せる不思議な愛嬌、年輪の笑顔。
両手をひろげて、言葉を空間に投げたら、それが歌。何もしていない。
日本の短歌を叫ぶ人なんかと共通しているものがある。
おそろしくスローの奇妙なリズムだが、自分のエモーションのリズムを
確立しているので、バンドは呼吸を汲み取って合わせるしかない。
5人して、舐めず、舞い上がらず、ぶっつけの“音楽の”セッションをしている。
引き受けて立っている。完全に自分独自の呼吸。唯一無似。
ジミーは我々の眼の前にふれる以前からもう自由に開放されている。
現れるやいなや、面前の私たちに放って与えてくれる。
その人間的な懐の深さには頭をたれるしかない。
ジミーが“ラッキー”と一言、空気中に置いた「ラッキー」は、パチンコ屋や、
飲み屋街の街頭で踏みつけにされたキャバクラのちらしにあるような、
安っぽい黄色やピンクのカタカナ英語の(らっき−!)ではない。
まるで秀作の油絵のように、暖かく、哀しく、幸せで、
深みの独自の色彩が浮かび上がった “Lucky・・・”
人生がつまっている。
ジミ−の(Lucky)みたいに、(愛)や(恋)や(男)や(おんな)や
(あか)や(きいろ)や(春)やら(秋)やら(雨)やら(雪)やら、
ひとつでもあんなに大切に扱ったことがあるだろうか?
生きながらにして、天国にとどいているんだよなあ、この人は。
ジミー以上に聴き手に感謝の念を起こさせる歌い手には会ったことがない。
▲トップへ戻る
【ジミースコット
ライブ】
この内容の引用、二次、三次利用等は固く禁じられておりますのでご注意ください。
他への転写、掲載もご遠慮くださいますようお願いいたします。
※プライバシーについての考え方
©2011
Breath Voice Training Lab. All Rights Reserved.
|